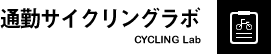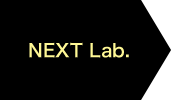通勤手段のひとつとして、今まさに注目されつつある自転車。交通渋滞や満員電車を避ける目的に加え、エコな取り組みのひとつとしても検討している企業が増えています。
しかし、いざ導入する場合は、ある程度のルールなどを設けるべきか、悩んでいる企業も多いでしょう。そこで、これから5回に渡り自転車通勤制度を導入する際に企業が検討すべきポイントをご紹介していきます。
INDEX
自転車通勤を導入する際のポイント
自転車通勤は、企業にとっては交通費支給の経費削減や、企業イメージの向上が期待でき、従業員にとっては健康維持や利便性の向上などが期待できる取り組みです。とはいえ、通勤手段のひとつともなれば、従業員の安全確保が重要になってきますので一定のルールを設けて、広く認知させる必要があります。
また、他の交通手段との併用などをはじめ、自転車特有の通勤スタイルも考えられますので、公共交通機関やクルマでの通勤とは異なる次のような検討すべき課題があります。
・経路と交通手段
・通勤手当
・交通事故ルールやマナーなど法規遵守
・損害保険等の加入
・事故の対応
これらは担当部署だけでなく、経営層も含め会社全体でじっくり検討すべき課題となりますので、1つずつ詳しく見ていきましょう。今回は、「経路と交通手段」についてです。
距離・経路をルール化

はじめに自転車通勤の距離と経路を決める必要があります。これは誰が見ても徒歩圏内と思うような短距離でも認めるのか、逆に遠すぎて困難ではないかと思うような距離でも認めるのかなどを検討します。また、距離・経路について企業は事前に次の3つを把握しておくことが重要です。
1.自転車通勤の経路、距離の合理性
2.通勤手当を支給する際の整合性
3.通勤途中の災害や事故発生の安否確認
これらのポイントについて詳しく見ていきましょう。
1.自転車通勤の経路、距離の合理性
自転車通勤の申請があったとき、客観的に見て通勤経路・距離に合理性があるかを判断する必要があります。基本的に通勤は自宅から会社までの往復になりますが、自転車通勤によって、一方通行の道路や時間規制の道路も利用できるようになる場合もありますので、そのような点から合理性を判断します。
2.通勤手当を支給する際の整合性
自転車通勤でも通勤手当を支給する場合は、申請された通勤距離について整合性があるのかを判断します。この判断には、もちろん通勤経路の把握が必要となり、従業員から不自然な通勤距離の申請(たとえば、徒歩通勤が可能にも関わらず申請)などがあった場合は自転車通勤を許可しないなどの処置が必要となります。
3.通勤途中の災害や事故発生の安否確認
万が一、通勤途中に災害や事故が発生し、従業員の安否確認を行うには、事前に従業員の通勤経路を把握しておく必要があります。特に自転車通勤と他の交通手段の併用を認める場合は、より複雑になりますので、細かく把握しておきましょう。
これらを踏まえ、距離・経路については以下のようにルール化していきましょう。
・通勤経路は合理的な経路を選択する
・通行規制など道路事情があるときは、他の経路での通勤を認めること
・自転車の通勤距離の範囲は○○キロメートル~○○キロメートル以内とする
公共交通機関との乗り継ぎ

先述の通り、自転車通勤では公共交通機関との乗り継ぎをするケースも考えられます。そのため、企業は自転車と公共交通機関を併用した通勤を認めるかどうかを検討する必要があります。この乗り継ぎをするようなケースでは、自宅や会社の最寄り駅が遠距離の場合などが考えられますが、子供の送迎があるなど、家庭の事情によっても必要になるケースが考えられます。ただし、通勤途中で私的な行為によって経路を離脱した場合は、通勤災害に認定されないケース(*1)もあるため、ルールを決めるとともに従業員には十分な周知が必要です。
*1: 通勤災害で認定されるケース・認定されないケースについては「自転車通勤導入に関する手引き」(国土交通省)を参照ください。
日によって異なる交通手段の利用の可否

自転車通勤は、他の通勤手段とは異なり、雨や雪などの天候によって利用できないケースも考えられます。そのため、日によっては異なる交通手段でも認めるなどのルール化が必要になるでしょう。
たとえば、「通勤する際の交通事情、天候などにより自転車以外の交通手段を認める」などの規定をルールブックなどに明記するとともに従業員には十分に周知しておくことをおすすめします。さらに「自転車以外の交通手段」については、公共交通機関やクルマ、バイク、徒歩など具体的に挙げておくことも重要です。
自転車通勤を実際に導入しようとすると、細かな部分においてもしっかりと検討が必要であることがわかります。一見すると難しそうなイメージになるかもしれませんが、既に運用している他の通勤手段についてのルールに沿って考えていけば、意外とスムーズに運ぶことができるでしょう。次回は、「自転車通勤手当」のルール化についてお伝えします。
マインドスイッチでは、自転車や自転車通勤による健康的で豊かなくらしを実現するための情報をこれからも皆様にお届けしてまいります。
More Contents
-

世界の自転車通勤事情ドイツ編
日本では2018年6月に自転車活用推進計画が閣議決定され、施策のひとつとして自転車通勤の促進が盛り込まれていま […]
通勤Life
2020年9月8日
-

世界の自転車通勤事情 調査 第4回オランダ編
英語でオランダはNetherlandsと書きますが、これは「低い土地」という意味。 現在でも国土の約1/4が海 […]
通勤Life
2020年10月21日
-

企業が自転車通勤制度を導入するときに検討すべきこと(3)~事故予防のルール・マナーや法規の遵守~
自転車通勤制度の導入にあたり、懸念されるリスクとして通勤中の事故が考えられます。地域によっては自転車専用道路が […]
通勤Life
2020年9月16日
-

企業が自転車通勤制度を導入するメリットについて
満員電車など、密になりやすい空間での新型コロナウイルスへの感染が危惧されるなか、密を避けた通勤手段のひとつとし […]
通勤Life
2020年8月13日